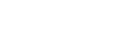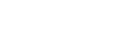小説 > Lil’Fairy Original Novel:13
Lil’Fairy Original Novel:13
「天に届いた優しい願い」
著者:空歩人
夕暮れ時、プリミューレ妖精協会の中庭には、お掃除の妖精三人娘が集まっていた。丸いテーブルを囲み、三人は色とりどりの折り紙で様々な形の飾りを作っている。
「残念ながら今日は曇り空ね」
空を見上げたエルノが言った。
「それは困ります。お空が晴れないと、二人が逢えなくなってしまいます」
リプーが訴えた。
「そうだね、リプー。でも、仕方ないよ。こればっかりはわたしたちの力じゃどうにもならないもの」
ヴェルがリプーを慰める。
「でも、可哀想すぎます……」
リプーが肩を落とす。
そこに笹を抱えたヴィスマルクがやってきた。
「エルノ、この笹はどこに持っていけばいいかな?」
「ありがとうございます、ヴィスマルクさん。それはテラスの中央にお願いします。立てられるよう台が用意してありますから」
ヴィスマルクは頷くと、テラスの中央に置いてあった台に笹を立てた。
「とても立派な笹ですね」
近寄ってきたヴェルが賞賛する。
「そうだろう? これなら、七夕の飾りにうってつけじゃないかと思って選んできたんだ」
ヴィスマルクは額にほんのりかいた汗をハンカチで拭きながら得意気に答えた。
「さすが、ヴィスマルクさんですね!」
エルノが紳士を褒める。
しかし、リプーだけが首をかしげて笹を見つめていた。
「どうしたんだい、リプー?」
ヴィスマルクは訊いた。
「えーとですね、どうして七夕には笹に飾りをつけるのかなと思って。笹はクリスマス・ツリーのモミの木のようなものなんですか?」
「そうね。なんでかしら?」
ヴェルも首をかしげる。
「笹はね、元々織姫様と彦星様へのお供え物の目印として祭壇のそばに用いられていたんですって。その後、笹自体が七夕祭りの象徴のようになったと聞いているわ。なんでも日本では、笹は昔から邪気を祓ってくれる神聖なものと信じられていたということよ」
エルノが説明する。
「へぇー」
「あ! そういえば、日本の神社では年末にする煤払いで、笹を使うって何かの事典で読んだことがあるわ。わたしが使うはたきと同じような効果があるんだとか」
ヴェルがはたきでポンポンとはたくようなジェスチャーをした。
「その通り。昔の日本では笹を掃除の道具として使っていたんだ。それに、エルノの言う通り、邪気を祓ってくれるお清めの道具であると信じられてきた。きっと笹が持つ強い生命力と殺菌力が一種の魔除けになると考えられたんだろう。そうそう、農家では田んぼの稲を荒らす虫を避ける道具としても使っていたそうだよ」
ヴィスマルクが解説する。
「うわー、笹ってすごいですね」
リプーは改めて笹を見た。
「さて、笹の由来も分かったことだし、飾りつけをしましょうか」
エルノの言葉とともに、リプーとヴェルは自分たちで作った飾りを笹につけていった。
「さぁ、最後は短冊よ」
飾りつけが終わると、エルノはリプー、ヴェル、そしてヴィスマルクに細長い紙を渡した。
「これにお願いごとを書くの?」
リプーは短冊を不思議そうに見つめた。
「そうよ。そして、その短冊を飾りと一緒に笹に飾ることで、書いた願いごとが叶うと伝えられているの」
各自はペンを取り、それぞれの願いを短冊に書いた。
数時間後の真夜中、プリミューレ妖精協会の誰もが眠りについていた。
中庭のテラスでは、お掃除の妖精三人娘とヴィスマルクの願いが込められた短冊が夜風に揺れている。
執事のヴィスマルクは、娘のような妖精たちのことを想い、短冊にこう記していた。
『みんなが健康でありますように』
向上心の高い真面目なエルノは『立派なお掃除の妖精になれますように』と、自らの願いを綴っていた。
おしゃべりが大好きなヴェルは『いつまでもみんなと仲良くお話しができますように』と、その胸の内を短冊に込めていた。
誰よりも心優しいリプーは、一年に一回、七夕の晴れた夜にしか会えない織姫と彦星のことを想い、こんな願いを短冊に書いていた。
『どうか今夜のお空が晴れて、織姫さんと彦星さんが逢えますように!』
そんなリプーの願いが天に届いたのか、それまで空を覆っていた雲はゆっくりと消えてゆき、星々が姿を現しはじめた。
やがて夜空の中央に天の川が形成されていく。
その両脇に一つずつ、ひと際強い光を放つ星が現れた。織姫星(ベガ)と彦星(アルタイル)である。二つの星は一年ぶりの再会を喜び合うように輝き続けた。
そして日が昇る寸前、織姫星からプリミューレ妖精協会のテラスへ向かって光の矢が放たれた。
翌朝、リプーは自分が書いた短冊に、ちょっと不思議なことが起こっているのに気づいた。

『ありがとう』
短冊にはそう書き加えられていたのである。
終