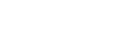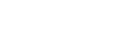小説 > Lil’Fairy Original Novel:06
Lil’Fairy Original Novel:06
「サンタクロースのピンチ!?」
著者:空歩人
昼過ぎから降り続いていた雨が夕方には雪へと変わり、森の木々もうっすらと白い化粧をしている。
森の奥深くにそびえたつ古城のような屋敷――プリミューレ妖精協会にも雪が積もり始めた。
その屋根の上に浮かんだ、ひとつの影。
影はゆっくりと移動し、東に位置する煙突へと向かっている。動きが軽やかではないのは、屋根に積もっている雪で滑らないように慎重になっているからだろうか。それとも、背中に大きな袋を背負っているからだろうか。
ようやく煙突まで到達すると、影は大きな袋を足下に置いて、大きく深呼吸をした。
「ふぅ……。さすがにこの寒さと大荷物では堪えるな……」
影はぽつりと呟いた。
そして、再び袋を持ち上げようとした、その瞬間。「ビシッ!」っと、腰の辺りに稲妻の衝撃が走った。
広間には大きな暖炉があった。その横には、天井の高さほどのモミの木があり、枝のあちこちにクリスマスのオーナメントが飾りつけられている。
「いい? つけるわよ!」
ヴェルはエルノとリプーに向かって手を振ると、手にしていたはたきを高く掲げた。さっと宙で弧を描き、はたきの先端をツリーに向ける。すると、一瞬、キラキラ輝く光の粉がツリーのてっぺんまで舞い上がり、ツリー全体に施されている電飾が点滅し始めた。

「うわぁ!」
「キレ~イ!」
エルノとリプーが声を上げる。
白い輝きを放つ豆電球。その光は様々な色をしたオーナメントに反射して、広間は七色の光彩で埋め尽くされた。
その美しさをうっとり眺める妖精三人娘。
しばらくすると、リプーがあることに気づいた。
「あれ?」
「どうしたの?」
ヴェルが尋ねる。
「あのね、この木はモミなのに、どうしてりんごがぶら下がっているのかなって思って」
「確かに言われてみればそうだね……」
ヴェルはリプーの疑問に同意した。
「もしかして、二人ともクリスマス・ツリーの由来を知らない?」
エルノが驚く。
「ツリーの由来って、なぁに?」
「わたしも知らないな」
「クリスマス・ツリーというのは、知恵の樹の象徴なの。ほら、エデンの園にあったと伝えられる二本の木のうちのひとつね。そして、最初の人間といわれているアダムとイヴが食べたのが知恵の樹の実。その実はりんごだったという言い伝え」
「ふーん。だから、ツリーにりんごを飾るの?」
「そういうこと」
「さすが、物知りのエルノね」
ヴェルが感心する。
「わたしは大好きな栗を飾りたいな」
「もう、リプーったら!」
ヴェルはリプーをたしなめた。
「まぁまぁ、ヴェル。今日はクリスマス・イブなんだから」
エルノが割って入る。
「それに、リプー。ツリーには飾れないけど、今夜のクリスマス・ケーキにはあなたの大好きな栗を使ったマロングラッセがたくさん載っているのよ!」
「うわぁ、本当に?」
「わたくしの大好きなシフォンケーキを、ヴェルの大好きなチョコレートでコーティング。トッピッグにはイチゴの代わりに、リプーが大好きな栗を使ったマロングラッセをデコレーション。名づけて、『お掃除の妖精スペシャル・クリスマス・ケーキ』よ!」
エルノがテーブルの中央に置かれたブッシュ・ド・ノエルを指差す。
「えっへん! お掃除の妖精きっての料理上手と呼ばれる、このわたしが作ったんだから味に間違いはないわよ」
ヴェルが得意気な表情でVサインをした。
「わぁい、早く食べようよ!」
リプーがさっそくケーキの前にある席に座った。
「ああ、ちょっと待って!」
エルノがリプーを制止する。
「なんで?」
「だって、まだヴィスマルクさんが来ていないもの」
「そういえば、そうよね。プレゼントを持って8時にはここに来るって話だったけど……」
ヴェルが壁掛け時計を見やると、針は既に8時30分を指していた。
「一体どうしたんだろう……?」
三人は心配になった。
クリスマスにはサンタクロースがつきものだ。今年も頑張ったお掃除の妖精三人娘にそのご褒美としてプレゼントを贈ろうと思いついた。だけど、単に渡すだけじゃ面白味がない。そこでサンタクロースの格好をして煙突から降り、暖炉から「メリー・クリスマス!」と華やかに登場するという粋な演出を思いついた。
しかし、ヴィスマルクの計画を邪魔したのは雪である。そして、予想以上に重かったプレゼント。結果、まさか煙突の手前でギックリ腰になってしまうとは……。
煙突の隙間から、楽しそうにはしゃいでいるエルノ、リプー、そしてヴェルの声が聞こえてくる。
はてさて、どうしたものかな?
サンタクロースの衣装は思いのほか温かく、どうにか寒さはしのげる。
だが、このまま屋根の上で淋しいクリスマス・イブを過ごすことだけは絶対に避けたいものだ。
どうやって助けを呼ぶべきかと深く悩むヴィスマルクなのであった。
終