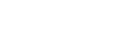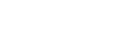小説 > Lil’Fairy Original Novel:14
Lil’Fairy Original Novel:14
「ヴィスマルクよ、永遠に」
著者:空歩人
本日を以って、こことはお別れである。紳士は改めてちいさな部屋の中を見まわした。
この部屋の家具、全てが思い出の品々だった。特に長年愛用し続けてきたブラックウォールナット製のデスクは、これまでの仕事を支えてきてくれた大切な友だ。
その表面をそっと撫でてみた。指先がところどころにある傷やくぼみに触れる。その感触は紳士の脳裏に数々のエピソードを呼び起こさせた。
今の役目に就くと決まった時、この身を一生捧げ、この部屋とともに生きていくのだと決意した。それなのに、まさかこんな日がやってくるなんて……。
紳士は胸に熱いものが込み上げてくるのをぐっと堪えた。
感傷にひたっている場合ではない。
紳士は椅子からすっくと立ち上がり、部屋をあとにした。
「たっ、た、大変です~!」
蒼ざめた顔のリプーが、長い髪をたなびかせながら勢いよく走り込んできた。
中庭のテラスで午後の紅茶を楽しんでいたエルノとヴェルがその声にびっくりする。
「どうしたの? そんなに慌てて」
「そうよ、リプー。まるでこの世の終わりみたいな顔して」
「だって、大変なんです!」
リプーは大親友の二人に必死に訴えた。
「だから、何がそんなに大変なの?」
「ちゃんと話してくれなきゃ、わたしたちには分からないわよ」
「ヴィスマルクさんが……」
「ヴィスマルクさん?」
「ヴィスマルクさんがどうかしたの?」
「……いないんです」
「えっ?」
「なに言ってるの?」
エルノとヴェルは、リプーの言っていることの意味が分からず、問い返した。
「だから、ヴィスマルクさんがいなくなってしまったんです」
「お散歩にでも行ってるのかもよ」
「執事室にはいないの?」
「その執事室が空っぽなんです!」
「えええっ!?」
状況をようやく理解したエルノとヴェルは、急いでリプーと一緒に執事室へと向かった。
ドアを開けると、リプーの言う通り、室内は空き部屋同然だった。それまで本がぎっしりと並べられていた本棚、ティーセットが置いてあった食器棚など、それらのどれもが文字通り空っぽだった。唯一残っているものは、『執事 ヴィスマルク』と記された卓上札だけであった。
「ねぇ、これってどういうこと?」
「まさか、家出しちゃったとか?」
「きっといつも迷惑かけているわたしたちに愛想を尽かして、執事のお仕事を辞めちゃったんです」
リプーは緑色の大きな瞳にうっすらと涙を浮かべた。
「まさか、そんなこと……」
「……」
涙目で悲しみを告げるリプーに、エルノとヴェルも返す言葉が見つからなかった。
三人の脳裏には、ヴィスマルクとの思い出が蘇ってくる。
いつもみんなのことを細やかに気遣い、優しく接してくれたヴィスマルク。その存在は協会に所属するお手伝いの妖精たち全員にとって、まるでお父さんのようだった。そんな大事な人であるヴィスマルクが、もうこの部屋にいない。
リプー、エルノ、そしてヴェルはその場に呆然と立ち尽くすしかなかった。
紳士は忘れ物をしていたことに気づいた。きちんと確認して出たつもりだったのだが、少しばかり感傷的になっていたせいで、ついうっかりしてしまったようだ。忘れ物を取りに行こうと、お別れした場所へと踵を返した。すると、その部屋の中に立っている三人娘の姿が目に入ってきた。
「みんな、どうかしたのかね?」
その様子をおかしいと感じた紳士は、心配になって思わず声をかけた。
しかし、三人は返事をするどころか、身じろぎ一つせずにじっとしている。
紳士は不思議に思い、開いていたドアをコンコンと叩いてみた。
それにより、三人のひとり、エルノが紳士の方を振り向いた。

「やぁ、エルノ」
「ヴィ、ヴィスマルク……さん?」
エルノはまるで幽霊でも見ているかのごとき表情で、驚きながら声を発した。
その声に反応し、リプーとヴェルも顔を上げてヴィスマルクを見た。
「こ、この部屋は一体……?」
ヴェルが動揺している様子で尋ねてくる。
「うん?」
「空っぽさんです」
目を真っ赤にしているリプーが言う。
「ああ、この部屋のことかね? 実はだね、この一年半ばかりお手伝いの派遣を希望される人たちが増えてきているんだ。それに、もうすぐ新しい妖精たちも加わることになっている。そこで、この部屋のスペースでは協会にいる全てのお手伝いさんたちを束ねるのは狭くて大変だろうと、理事長が広い部屋を用意してくれたんだよ。ほら、向かいの応接室をリフォームしてね」
ヴィスマルクは廊下のちょうど反対側にあるドアを指さした。
「なぁーんだ、そういうことだったんですね」
「ヴィスマルクさんがいなくなってしまったのかと思い、びっくりしました」
「でも、よかったじゃない。こうやってヴィスマルクさんがどこにも行っていないって分かったんだから」
三人娘はほっと安堵して胸を撫で下ろした。
そういえば、執事室を移ることは誰にも伝えていなかったか。
ヴィスマルクは驚かせてしまったことを詫びると、置き忘れていた卓上札を手に取り、それを三人娘に向けた。「この通り、わたしはこれからもずっとここの執事だよ」と、優しく微笑む。
それから、お掃除の妖精三人たちは、ヴィスマルクの新しい執事室への引っ越しを手伝った。
ヴェルははたきを操り、整理の魔法であっという間に本棚に本を収納させていった。
エルノはほうきで部屋の隅のホコリをキレイに掃いたあと、食器棚にティーセットを丁寧に並べていった。
リプーは床にモップを滑らせ、ぞうきんがけし、見事ピカピカに磨き上げた。
ヴィスマルクは書類の整理をしながら、お手伝いをしてくれている彼女たちの仕事ぶりを見て、とても誇らしく感じた。
もう彼女たちはれっきとした立派なお手伝いさんだ。この先何があろうと彼女たちならきっと上手くやっていける。自分が心配することはもう何もないだろう。
「ところで、ヴィスマルクさん。さっき、新しい妖精たちが加わるっておっしゃっていましたよね?」
エルノが興味深そうに尋ねた。
「おお、そうだった。みんなにはまだ話していなかったね」
「うわぁ、新しい仲間が増えるんですか? それはとっても楽しみです」
リプーは緑色の大きな瞳を輝かせた。
「何が専門のお手伝いさんなんですか?」
ヴェルも好奇心の色を隠せない。
「実はだね……」
ヴィスマルクは新しい妖精たちについて語りはじめた。それは、お掃除の三人娘もびっくりしてしまうほど不思議な特技を持った妖精たちだった。
その新しい妖精たちのお話は、また別の機会に……――。
Please be well until we meet again.
終