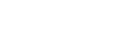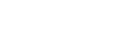小説 > Lil’Fairy Original Novel:11
Lil’Fairy Original Novel:11
「悩んだときの解消法」
著者: 空歩人
「ハッ、ハッ、ハッ……」
呼吸が一定のリズムを刻んでいる。少し疲れを感じはじめていたが、ペースは落とさない。このままゴールまで走りきるつもりだ。
ヴェルは森の中を走るのが大好きだった。緑の中を風とともに駆け抜けると、心が洗われるような気がするからだ。
スタートしてから約1時間。そろそろ戻ろうかと思った矢先に、突然、大粒の雨が降ってきた。
ヴェルは大慌てでプリミューレ妖精協会の屋敷へと足を向けた。
「おやおや、濡れてしまったね。これを使うといい」
屋根がある中庭のテラスまで戻ると、席に座っていた執事のヴィスマルクがタオルを差し出してくれた。
「ありがとうございます」
ヴェルは礼を言ってタオルを受け取ると、濡れた髪の毛やトレーニングウェアをさっと拭いた。
「これ、洗ってからお返ししますね」
「いやいや、そのままでいいから」
ヴィスマルクは手を振って、大丈夫というジェスチャーをする。
「お天気だったのに突然降りだしたので、ビックリしました」
「本当だね。まさに狐の嫁入りっていうやつだな」
「え? 雨が狐の嫁入り?」
「その地方によって呼び方が違うんだが、日本では一般的にお天気雨のことをそういうんだ」
「そうなんですね」
「うむ。晴れているのに雨が降るという不思議な現象のことを、その昔、狐は妖怪のように人間を化かす力があるという言い伝えにひっかけて、そういうようになったんだとか」
「それ、面白いですね。でも、どうして狐が人間を化かすという話になったのでしょう?」
「うーん、どうしてかな。日本で狐が人間を化かす妖怪だという概念は、もともと仏教と深く関わりがあるようだね。中国に伝わる九尾の狐のお話に深く影響を受けているらしい。だけど、本当のことを知る者は誰もいない。昔の日本人は、人里離れた山や森で暮らす生き物である狐に、何かしら未知の力を感じたのかもしれないね」
「なるほど。だけど、そんな話をリプーが聞いたら、『狐さんは嘘つきさんだから、気をつけないとです』とか言いだしそうですね」
ヴェルは親友のことを思い浮かべた。
「あはは。そうかもしれないな」
二人が笑っていると、次第に雨がやみ、空に大きな虹がかかった。
「うわぁ~!」
「おぉ!」
七色に輝く虹はまるで空にかかる大きな橋のようだった。
ヴェルはしばらく幻想的な光景を見ながら、虹はどことどこを結ぶ橋なのだろうと考えてみた。

ヴェルの様子を見て、ヴィスマルクが声をかけた。
「ところで、ヴェル。何か悩みごとでもあるのかな?」
「え? どうしてそんなこと訊くんですか?」
「きみは研修生の頃から、何か悩むと森の中をランニングしていただろう。今日も何かあったのかな、と……」
「えーと、それは……」
ヴェルは口ごもった。
「いやいや、何も無理してわたしに打ち明ける必要はないんだよ。ただね、アメリカのハワイ地方では『雨が降らねば、虹はない』ということわざがあってね。辛いことや悲しいことがあっても、それを乗り越えたら、きっといいことがあるはずだよ」
「そっか……」
ヴェルはヴィスマルクの言葉を噛みしめるように頷いた。
「ありがとうございます」
ヴェルは礼を言って部屋へ戻ろうとヴィスマルクに背を向けたが、数歩進んだところで振り返った。
「ところで、ヴィスマルクさん。ひとつ訊いていいですか?」
「なんだね?」
「確か、ヴィスマルクさんもダイエットのためにランニングを始めるって言ってましたよね?」
「あ、まぁね……」
「それ、続けていらっしゃるのでしょうか?」
「それは……」
ヴィスマルクは返答に困り、口ごもった。
「おはぎとか、甘いものをたくさん食べているんですから、運動もしてくださいね。そうでないと、狐じゃなくて、お腹がポンポコポンの狸さんになってしまいますよ」
ヴェルは悪戯っ子みたいな表情を浮かべると、その場から去っていった。
痛いところを突かれてしまった。ヴィスマルクはひとりテラスに残り、ヴェルが走ってきた森へ通じる道を眺めた。
いかん、いかん。三日坊主どころか、口先だけで一度も実行に移していないではないか。しかし、いきなりヴェルのように長い距離を走るのは無理である。最初は、せいぜい協会の敷地を一周するぐらいだろうか。
うーん……。
ああ、おはぎが食べたい。
何か悩みごとができると、ついつい甘いものが食べたくなるヴィスマルクなのであった。
終