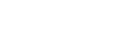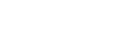小説 > Lil’Fairy Original Novel:12
Lil’Fairy Original Novel:12
「いつもありがとう」
著者:空歩人
プリミューレ妖精協会の執事であるヴィスマルクは、その日の最後の事務仕事を終えると、執事室を出た。
すると、廊下の先でこちらの方をじっと見ていたリプーと目が合った。
「やぁ、リプー」
ヴィスマルクはモップの精に声をかけた。
しかし、リプーはヴィスマルクの姿を認めると、何故か表情をこわばらせた。
「どうもです」と、小さな声でお辞儀をしたかと思うと、その場から慌てて逃げるように食堂の方へ走っていってしまった。
はて、どうしたものか?
最近寝不足のわたしの顔が怖かったのだろうか?
いやいや、まさかそんなことはないだろう。
しかし、何故?
そういえば、リプーだけではない。今日は他のお掃除の妖精たちの態度が少し変だった。
朝、廊下ですれ違ったヴェルは、軽く会釈をしてくれたものの、何故か気まずそうな表情を浮かべた。見れば脇に大きな包みを抱えていたので、「それ、運ぶのを手伝おうか?」と訊けば、「大丈夫です」とそっけない一言だけが返ってきた。それどころか、わたしに近寄らないでくださいオーラを漂わせていた。包みには何か大切なものが入っていて、きっと他の誰にも見せたくないのだろう。しかし、ヴェルの、自分を避けるような態度が、ちょっと悲しかった。
そして、昼食時に食堂で顔を合わせたエルノも笑顔で挨拶はしてくれたものの、同じく、なんとなく自分を避けていたような気がする。今後の派遣先について夕食頃に話をしたいと提案したら、「今日は忙しいので、明日にしてください」と言われてしまったのだ。普段なら、どんなに忙しくても積極的に話をする時間をつくってくれるはずなのに、どうしてだろうと不思議に思った。
三人とも日々笑顔を絶やさないし、冗談も交えて会話を楽しんでくれる。それなのに、今日に限って、何故か三人の態度がよそよそしい。
思春期? 反抗期?
あるいは、彼女たちに嫌われるようなことを何かしてしまったのだろうか? そんな記憶はないのだが……。
理由がなんであれ、ともかくヴィスマルクは淋しい気分でいっぱいだった。
「はぁ」
ヴィスマルクはため息をつくと、重い足取りで食堂へ向かった。
食堂のドアを開けた瞬間、ヴィスマルクの視界に飛び込んできたものは、「パン!」というクラッカーの音とともに、キラキラと輝いて宙を舞う虹色の紙テープだった。
「ハッピー・ファーザーズ・デイ!」
見れば、食堂にはプリミューレ妖精協会に所属する妖精たちが全員集まっていた。その中心にいるのはお掃除の妖精であるエルノ、リプー、そしてヴェルだった。
突然のことに驚き、言葉を失っているヴィスマルク。そんな彼に向かってエルノが一歩前に出た。
「今日は父の日です。いつもわたくしたちを優しく見守りながら、色々とお世話をしてくれて、本当にありがとうございます。わたしくしたちの、いえ、この協会のお父さんのような存在であるヴィスマルクさん。今日はわたくしたちから日頃の感謝を込めて、父の日のお祝いさせてくださいね」
そう言うと、エルノはヴィスマルクに大きなバラの花束を差し出した。
「あ、ありがとう」
ヴィスマルクがようやく口を開く。
すると、今度はリプーとヴェルが前に出てきた。二人は大きな包みを持っている。それは今朝、ヴェルが抱えていたものだった。
「これはわたしたちからのプレゼントです。気に入ってくださるといいのですが」

ヴィスマルクは花束をテーブルに置くと、包みを受け取った。
「開けても、いいかね?」
「もちろんです」
リプーとヴェルが笑顔で頷く。
グリーンのリボンを外して、キレイな包装紙を解くと、中からふわふわの枕が出てきた。
「最近、あまりよく眠れていないようですから、その枕でぐっすり眠って疲れをとってもらえたらと思って」
ヴェルがウインクする。
「これでお羊さんを数えなくても、ぐっすりスヤスヤです!」
リプーがニコッと笑う。
いつの間にかヴィスマルクの瞳は涙で溢れ返っていた。
「みんな、ありがとう……」
これまでプリミューレ妖精協会に所属する若い妖精たちを自分の子供のように見守ってきたヴィスマルク。彼の優しさはそこにいる全ての妖精たちにちゃんと伝わっているのである。先ほどまで感じていた淋しさはすっかりどこかへ飛んでいってしまい、今は幸せな気持ちでいっぱいだった。
これからもみんなの父親として、そして執事として、この協会をしっかりと支えていこう。そう心の底から誓うヴィスマルクなのであった。
終