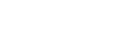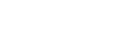小説 > Lil’Fairy Original Novel:02
Lil’Fairy Original Novel:02
「紅茶とスイーツ」
著者:空歩人
お手伝いの妖精たちを束ねるプリミューレ妖精協会の執事・ヴィスマルクにとって、午後の3時に食堂のテラス席で中庭を眺めながら紅茶をたしなむことが何よりの楽しみだった。特に紅茶党というわけではないのだが、庭の花々の香りを楽しみながら時間を過ごすには珈琲だと匂いがきつすぎると感じていた。
その日、ヴィスマルクがいつものようにたくさんのお湯が入ったポットとティーセットをトレイに載せてテラスへ行くと、そこには先客たちがいた。お掃除のお手伝いであるエルノ、リプー、ヴェルだった。
「ごきげんよう、ヴィスマルクさん」
三人のリーダー的存在であるエルノが笑顔で挨拶してきた。
「ごきげんよう、エルノ。それにリプーとヴェルも」
「ごきげんようです、ヴィスマルクさん」
「ごきげんよう」
「そうだ。きみたちも紅茶を飲むかな?」
ヴィスマルクは三人に提案した。
「はい」
「ぜひ」
「わたくしも頂きます。あ、カップ、取ってきますね」
エルノは小走りに食堂へ行き、自分たちの分のティーカップを運んできた。
「それじゃ、そこに座って」
ヴィスマルクは三人を座らせると、ティーポットに茶葉をスプーンで五杯入れ、たっぷりのお湯を注いだ。
「あれ? ヴィスマルクさん、何故茶葉を五杯入れたのですか?」
リプーが不思議そうにヴィスマルクの手元を見ていた。
「うん?」
「そういえば、そうよね。ここにいるのは四人だから、四杯でいいような気がする」
ヴェルがリプーの言葉に頷く。
「それはだね」、ヴィスマルクはポットに蓋をすると、席に深く座った。
「確かにここには四人いる。だから、それぞれに一杯ずつ。エルノ、リプー、ヴェル、そしてわたしの分。だけど、美味しい紅茶をいただくためには、茶葉をじっくりと蒸らしてくれる大切なポットへの敬意を払わないとね」
「なるほど。それでもう一杯なんですね」
エルノはヴィスマルクの言葉に感心した。
「その通り。それに薄いやつはどうも味気ない。茶葉の深い味わいを引き出すには、それなりの濃さが必要なんだよ」
「さすが、ヴィスマルクさん。こだわりの紳士ですね」
ヴェルが頷く。
「こだわりってほどでもないかな」
老紳士はちょっと照れくさそうに笑った。
「うーん……」
だが、リプーは不思議そうにポットを見つめている。
「リプー、どうしたの?」
「えーと、ポットさんも紅茶を飲むのかなと思って……」
その言葉に、一瞬誰もが口を閉じたが、直ぐに大きな笑い声が響いた。
「えええ。なんでみんな笑うの?」
「ポットが紅茶を飲むわけないじゃない」
「そうよ、リプー。ポットは紅茶をいれる道具なのよ」
「だってさ、きっとポットさんも喉が渇くはずだもの……」
心が優しいのか天然なのか、相変わらずのリプーの言葉。それにエルノとヴェルが絶妙な突っ込みを入れる。
いつものことながらこの三人の会話は心を和ませてくれる。お手伝いさんとしての個々の能力もたいしたものだが、この三人の仲の良さはいずれ何に対しても決して負けないチームワークを発揮して、これからの協会を引っ張っていく存在になってくれることだろう。そう思うと、ヴィスマルクは心から安心できるのであった。
「ねぇねぇ。こうやって美味しい紅茶を飲んでいると、甘いものが食べたくならない?」
エルノがみんなに問いかける。
「なるなる」
「わたしも」
「紅茶に合うスイーツといったら、やっぱりシフォンケーキだとわたくしは思うのよね」
「わたしはモンブランが一番だと思います。マロンの香りと味は紅茶の美味しさを際立てます」
「いやいや、リプー。確かにモンブランは美味しいけど、マロンの持つ癖はちょっと邪魔すると思うの。その点、シフォンケーキはシンプルだけど、計算されて焼かれた生地の甘さは紅茶の香りを何よりも引き立ててくれるんじゃないかしら」
「えええ。そうかな?」
「ノーノー。エルノもリプーもちっとも分ってないな」
ヴェルはちょっと呆れた表情で二人の間に割って入った。
「ヴェルちゃん、他にもっといいスイーツがあるの?」
「もちろん! 紅茶だけではなく、どんな飲み物にも合うし、美容と健康にも効果的な万能のスイーツが世の中にはあります!」
ヴェルはそう言うと、ワンピースのポケットからある物を取り出した。
「これよ、これ」
「チョコレート!?」
エルノはヴェルの手元を見て驚きの声を上げた。
「そう。チョコレートこそ、究極のスイーツだわ」
ヴェルは手にした板チョコのパッケージを破くと、「パリッ」と音を立てて食べた。
「わあ、いいな」
リプーは緑色の大きな瞳で羨ましそうにヴェルの板チョコを見つめる。
「少しあげようか?」
「うん」
ヴェルはニコッと笑うと、板チョコの一片を割ってリプーに差し出した。
「ありがとう」

「ちょっと、リプー。モンブランはどうなったの?」
二人のやりとりを見ていたエルノが訊いた。
「だって、今目の前にあるのはチョコレートだもん」
リプーは笑顔で板チョコをほおばった。
その美味しそうなこと。「自分にも少しくれないか」とヴィスマルクは思わず言いそうになってしまった。
いかん、いかん。最近は健康を考えて好物のあれさえ我慢しているのだ。
実はヴィスマルクにとって紅茶に合うスイーツといったら、おはぎなのである。しかし、それは誰も知らない内緒の話であった。
終