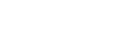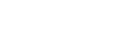小説 > Lil’Fairy Original Novel:05
Lil’Fairy Original Novel:05
「良薬は口に苦し?」
著者:空歩人
心なしか、熱が上がってきたように感じる。呼吸は苦しく、顔中がほてってきた。
やはり風邪か……?
ヴィスマルクは毛布を首元までたくし上げ、目を閉じた。体温計で測らずとも、額に手を当てただけで熱があることは分かる。むしろ正確に何度あるのかを知ってしまったら、余計に具合が悪くなってしまいそうだ。今は何より眠ってしまった方がいいだろう。
体調に異変を感じたのは、今朝からのこと。朝食を終え、執事室に入った時から、喉に違和感を覚えた。だんだんと痛みに変わっていき、昼食後には鼻水が出て寒気さえ感じ始めた。
これは大事をとって早めに部屋へ戻った方がいいかもしれない。幸いにも、今日は特に急いで片付けるべき仕事はなかった。
ヴィスマルクは理事長に断りを入れると、夕方前には自室に戻り、ベッドの中にもぐり込んだのであった。
しかし、それからずっと寝つけずにいた。
体調が悪くなると何故か心細くなるものだ。普段は気にもしないが、こうやってひとりで横になっていると、世の中の物事が自分に関係なく進んでいるように感じてしまう。置いてきぼりにされてしまったような淋しさが込み上げてくるのだ。
そんなことをあれこれ考えていると、いたずらに時間が経ち、気がつけば壁の時計は既に夜の7時過ぎをさしていた。
食欲はないが、薬を飲むためにも何か口に入れた方がいいかもしれない。そう思っていると、ドアをノックする音が響いた。
「ちょっと待ってもらえるかな」
ヴィスマルクはベッドから起き上がってガウンを羽織り、ふらついた足取りで来客を迎えに行った。
ドアを開けると、トレイを持った少女が立っていた。お掃除の妖精、エルノである。

「こんばんは、ヴィスマルクさん。お加減は如何ですか?」
「おや、エルノ。一体どうしたんだい?」
「理事長からヴィスマルクさんが体調を崩して早めにお部屋へ戻ったとお聞きしたので、わたくし頑張ってスープを作ってきました」
エルノはスープパンとお皿が載ったトレイを差し出すように見せると、「入ってもいいですか?」と尋ねた。
「ああ、もちろんだとも。ありがとう」
ヴィスマルクはエルノを室内に招き入れると、ダイニングテーブルへと案内した。
「わざわざすまないね」
「いいえ。食堂にお姿が見えなかったので、よほど具合が悪いんじゃないかと思って」
「絶好のタイミングというのはまさにこのことかな。薬を飲むためにも、ちょうど何か口に入れようと思っていたところさ」
「それはよかったです」
エルノは笑顔で答えると、湯気の立つスープパンからお皿にスープを注ぎ、ヴィスマルクの前に置いた。
「さぁ、これを飲んで温まってくださいね」
「ありがとう」
ヴィスマルクはスプーンでスープをすくい、口へと運んだ。
「うん? こ、これは……」
初老の紳士は思わず声を上げた。その味に舌が反応し、危うく口から出るところだったが、我慢して飲み込んだ。
「……まさか、お口に合いませんか?」
エルノは不安そうにヴィスマルクを見つめた。
「あ、いや、そういうわけじゃないんだ」
ヴィスマルクは無理矢理笑顔をつくって答えた。
「ただこの味、確かどこかで……」
「母より直伝の、特製スープなんです」
「ああ、なるほど」
そういうことか。ヴィスマルクは納得した。いつの間にか彼の脳裏には遠い記憶が蘇ってくる。
あれはまだ自分に白髪が一本もなかった頃。あの方はまだここの研修生だった。執務に追われて体調を崩し、今日みたいに寝込んだ時があった。そして、自分を心配してくれたあの方が今夜のエルノのようにスープを持ってきてくれたのだ。あの時の、あの味と全く同じである。
「あのう、どうかしましたか?」
エルノは尚も不安そうな表情でヴィスマルクを見つめていた。
「いや、なんでもないよ。大丈夫」
「でも……」
「このスープのお蔭で身体が温まって、今夜はゆっくり休めそうだよ」
「本当ですか?」
「もちろん」
その言葉に、エルノは笑顔を取り戻した。
「ところで、このスープには何が入っているのだろう? お母様直伝のレシピを教えてくれるかね?」
「はい。風邪に効くシナモン、シソ、ショウガ、長ネギ、そして香菜が入っています。特に母もわたくしも大好きな香菜はたっぷりと刻んで入れてあります」
エルノは笑顔で答えた。
ギクッ!
ヴィスマルクは風邪による悪寒とは別の、背筋に冷たいものを一瞬感じた。
臭覚や味覚が麻痺していて気づかなかったが、あの味はやはり香菜だったのか……。あの方直伝というのであれば納得である。あの方も香菜が大好きだった。
ヴィスマルクは香菜、すなわちパクチーが大の苦手なのである。しかし、そんなことは自分を気遣ってスープを作ってくれた優しいエルノに口が裂けても言えないヴィスマルクなのであった。
終